DESTINATION RESTAURANTS
By TAEKO TERAO
2月上旬、ジャパンタイムズ本社(東京都千代田区)にて、5回目を迎える「Destination Restaurants 2025」の選考会が行われた。今年も引き続き、審査員は辻芳樹、本田直之、浜田岳文の3氏。日本各地を食べ歩いたなかから、100店以上の候補を抜き出し、そこから約30店まで絞り込み、さらに今年の10店を選出した。選考対象となるのは、2021年(第1回)から2024年(第4回)に選出された40店を除外した「東京23区と政令指定都市を除く」日本各地のあらゆるジャンルのレストランだ。
3人の審査員は続々オープンする地方の新店をチェックする一方、かつて候補に上がりながらも「時期尚早」と見送った店にも再び足を向けて、その成長を確認してきた。その結果、今回は富山県『ひまわり食堂2』が「The Destination Restaurant of the year 2025」に選ばれた。
審査員のひとり、辻は言う。「この賞はシェフの技術を称賛するものとも言える。『ひまわり食堂2』オーナーシェフ、田中穂積氏が作る料理は素朴だが、基礎技術がしっかりしている。そのことをシェフ本人が自覚するとさらに成長できるはず」。
本田が今回、特に推した一軒は羊牧場併設レストラン、北海道『ファームレストラン クオーレ』。「素晴らしい羊を育てている牧場が飼育、加工、調理まで行っている。新鮮な羊の内臓をいただける貴重な場所」と賛辞を送る。
また、これまでガストロノミーな店が少ないと目されてきた四国地方の店が初めてリスト入りした。その店が愛媛県の『くるますし』だ。浜田はこの店について、こう語る。「ここ2〜3年で料理のクオリティが格段に上がり、遠くからでもわざわざ行きたい店へと成長を遂げた。オーソドックスな江戸前寿司を踏襲した店として、全国で10本の指に入る」。
都会に集中していた技術が地方に広がれば、日本列島全体の魅力が増す。そんなことがわかる10軒となった。

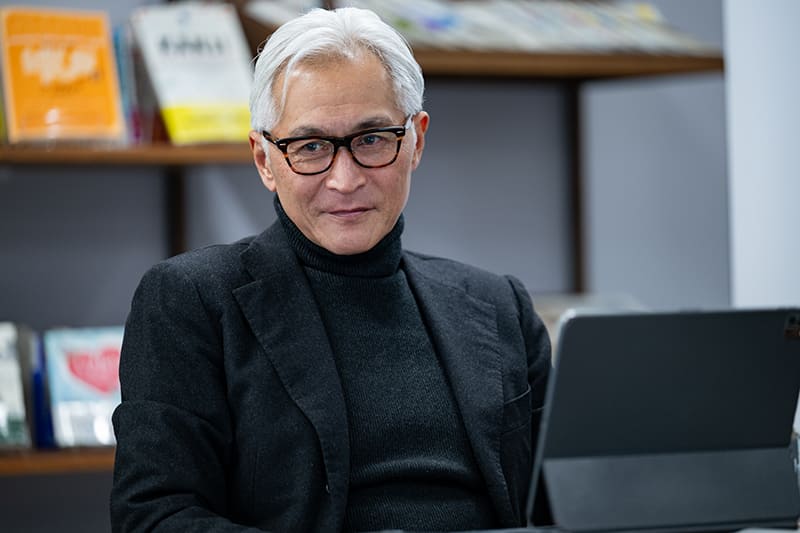
辻調理師専門学校 校長、辻調グループ 代表
私たち審査員があるレストランやシェフを選ぶということは、彼らが料理で表現している、その地域全体を選ぶということでもある。地方のシェフたちはゲストにわざわざ来てもらうために進化してきたが、今年は改めて彼らの底力、技術力を感じる。例えば、未利用魚のように、かつて捨てられていたような食材をガストロノミーな料理に仕上げるには技術力が必要になるが、「Destination Restaurants」に選出されたシェフたちの能力は国内においても高い水準にあり、優れた技術と創造性を持っています。こうした卓越した飲食店の存在は、国家政策としてインバウンド客を呼び込むための強力なツールともなっている。
今年も含めて「Destination Restaurants」で選ばれた50人のシェフたちはさまざまな困難をくぐり抜けて、料理を作るとともに生産者を育てるという料理人にしかできない仕事に取り組んできた、ある種のサバイバーでもある。そんな彼ら、つまり地域を表現し、啓蒙する技術者をこのアワードを通じて応援したい。この賞をきっかけに、もっと発言力をもって、地域の食を変えていってもらえたら嬉しい。そうした発言力は技術の裏付けがあってのものであり、シェフ同士や生産者がつながるためにも欠かせない。
大分県『日本料理 別府 廣門』店主、廣門泰三氏や石川県『オーベルジュ オーフ』シェフ、糸井章太氏はまだ若いので発展途上にあると言える料理人だが、確かな技術をもつ人たちなので、もっと自分の世界を究めていくと期待している。料理は結局、その人の人格や人生が出るもの。地方での経験を通じて、独創性を高めてほしい。

レバレッジコンサルティング株式会社代表取締役社長
年々、「おいしいものを作れば、人は地方に足を運ぶ」ことを料理人も理解するようになって、地方で独立する料理人が増えてはいたが、今年は特にその傾向が顕著になっている。鹿児島県大隅半島に位置する『センティウ』をはじめ、今回はたどり着くまでが困難なレストランが何軒も候補に上がった。行く方は大変だが、過疎が問題視されているような地域にガストロノミーな店が1軒でもできるインパクトは大きい。1軒できると、その跡を追って、数軒レストランができる例が各地で見られるからだ。一方、東京のベッドタウンにも「Destination Restaurants」にふさわしい店が増えている。埼玉県『レストラン カム』は新宿から電車で約1時間ほどのロケーションだというのに、自家菜園で作った野菜や近所の野草をふんだんに使って料理を作っているのがおもしろい。地方のレストランは集客が難しい分、いかにコストを下げるかが問題となる。食材の原価は安いが、自分で野菜を育てればその分、労力が必要なうえに災害があれば作物は台無しになるなど、コスト以外の苦労も多い。『田舎の大鵬』も京都府といえども綾部市という、中心から遠い場所にある。ここでは僕自身が自分の手で食材となる鶏を絞めて、息絶えたところをシェフが調理し、まさに「命をいただく」という経験をした。都会では絶対にできない体験。飼育から調理まで一貫させている『ファームレストラン クオーレ』もそうだが、一部の地方の料理人の食との向き合い方はより壮大になっている。

株式会社アクセス・オール・エリア 代表取締役
今年はこれまで選出されなかった県のレストランがリストインした。美食のイメージがあまりない埼玉県のほか、食材の産地としては有名だが、ガストロノミーなレストランが少ない愛媛県や鹿児島県、茨城県からも選ばれ、日本各地の食のレベルが高まっているのを感じる。今、富山県で『ひまわり食堂2』や「Destination Restaurant of the year 2021」を受賞した『レヴォ』が密に連携をとっているように、茨城県でもここ数年でジャンルを超えたシェフたちのつながりが強くなっている。地元食材を使うのはもちろん、江戸時代に茨城エリアを治めていた徳川家に伝わるレシピをもとに県内のレストランやホテルが料理を作るイベントを行うなど、興味深い取り組みを行っている。つくば市『ノンナ・ニェッタ』はその代表的なレストランとして選んだが、今後、同県からは続々、入選するだろう。同じエリアでレベルの高い店が何軒もあると、ガストロノミー・ツアーを組むこともできるので、インバウンド対策としても可能性を感じる。鹿児島『センティウ』は大隅半島の魚や肉を使いつつ、どの皿も野菜が主役になるような仕立てになっている。僻地にあり、基本的には鹿児島空港からレンタカーで行くような場所だが、もっと早く行けばよかったと思うくらい素晴らしい。調味料も控えめでナチュラルな味わいなので、ひと口ですぐ理解できるような料理ではないが、だからこそ応援したい。これからも地方で頑張っているのに知られていないようなシェフたちに光を当てていきたい。