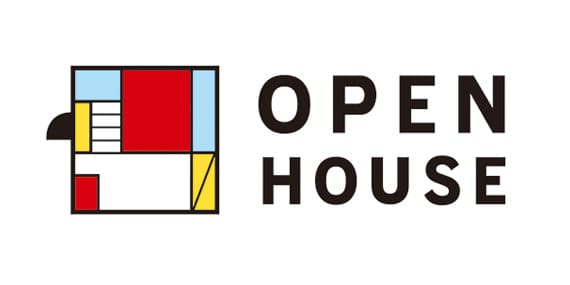Destination Restaurants
2021 and 2022
「Destination Restaurants」は、ジャパンタイムズが主催する日本発信のレストランセレクション。
“日本人が選ぶ、世界の人々のための、日本のレストランリスト として” 2021 年に発足しました。
「日本の風土の実像は都市よりも地方にある」と考えること、
また、「地方で埋もれがちな才能の発掘を目指す」こと、
「既存のセレクションとの差別化を図る」ことから、
特に日本の地方にあるレストランに限定して選んでいます。
お目当てのレストランがあるから、わざわざ日本の地方へと出かける。
このリストは、そんな旅を提案します。




「日本発信のレストランセレクションを」がこの企画の発端である。“日本人が選ぶ、世界の人々のための、日本のレストランリスト”を作るべきではないか。そんな議論から「Destination Restaurants 2021」は立ち上がった。
本題に入る前に、少しだけグルメガイドの歴史を振り返ってみよう。1900年創刊の「ミシュラン」、1969年創刊の「ゴ・エ・ミヨ」など、メディア独自の審査基準と調査に基づく格付け型ガイドブックが権威を誇ったのが20世紀。21世紀に入ると、インターネットの普及と共にカスタマーレヴューによる得点型ガイドが活発化した。また、2002年に英国の出版社が始めた「世界ベストレストラン50」、07年にNY在住のレコード会社経営者のブログから始まった「OAD(Opinionated About Dining)」など、世界を旅する食通によるランキングがレストランシーンを賑わせる。地域も料理ジャンルも取り払った境界のないランキングの活況は、都市ごとの格付けからグローバルでフラットな地平での競争への移行でもあった。
「東京は世界一星の数が多い都市」と言われるように、概して日本のレストランに対する評価は高い。しかし、ランキングやガイドの多くは海外の評価機関を母体としている。ワールドワイドな視点や価値観で選ばれる反面、日本の風土や精神性の細部にまで目が行き届いているかと言われれば疑問だ。
「1897年に創刊されたジャパンタイムズは、当時日本にあった、外国人が外国人の目で見た日本を伝える英字新聞では日本が伝えたい情報が発信されていない、という課題を解決するために、福沢諭吉や伊藤博文などの支援でスタートしたという歴史があります。そのフィロソフィの上に立ち、日本人が選び、伝えたい、オーセンティックな日本の食文化を世界に発信しようとの思いがこのセレクションのバックボーンにある」と社主の末松弥奈子は語る。





選考にあたったのは、辻芳樹氏、本田直之氏、浜田岳文氏。国内外のレストラン事情に精通し、何よりレストラン文化を愛してやまない3人である。
彼らはまず選考の前提条件として「東京23区と政令都市を対象から外す」という大胆な決断を下した。理由の第一は、日本の風土の実像は都市よりも地方にあること。第二に、このセレクションが地方に埋もれがちな才能の発掘に寄与するためだ。第三に、既存のセレクションとの差別化の意味もある。ガイドやランキングを見比べれば一目瞭然だが、ランクインする顔ぶれは類似し、かつ固定化しがち。新たに立ち上げる以上、独自的で革新的なリストを目指したという。「いい意味で型が固まり切っていない、これから進化していく10店を選んだ」と浜田氏は言う。
料理人がいることで立ち上がる景色(ヴィジョン)がある――その例証が世界各地から報告されているのが、昨今のガストロノミー界の動向である。動植物の生態、地形や地質、気候、季節の移ろい、人間の創造性、伝え継いできた知恵や技など、レストランとは自然と人間の営みをトータルで映し出す装置と言っていい。
「元来、欧州では、高い評価を得る店は概して不便な場所にある」と、本田氏と浜田氏は口を揃える。「何時間もかけて車を飛ばしてたどり着くような環境の中で、そこでしか手に入らない食材を使い、そこでしか味わえない体験を提供する店が支持を得る」。代表例として、辻氏はフランス・オーベルニュ地方のミシェル・ブラスの名を挙げる。「ブラスはオーブラックの土地と一体化して、風景も植生も生活文化も工芸品も包括的に取り込み、大地の劇場として存在している全方位型のレストラン」。
「この数年で、日本でもブラスのような店が増えてきた」という実感が3人にはある。料理人の探求がより素材へ、素材の生産方法や土壌や環境へ、すなわち料理の源流へとさかのぼっているからだろう。田畑で野菜や米の栽培をする、山菜やキノコを採集する、釣りや狩猟を行なう、肉加工品や発酵食品作りを手掛ける、ブドウを栽培してワインを造るといった自給自足型の料理人が存在感を発揮するようになった。「地産地消」ならぬ「自産自消」という言葉も登場した。レストランを生産から消費まで生命体の循環の舞台と捉え、より良き食のあり方を探る場と位置付ける料理人も少なくない。そう志向し始めた時、都市はもはや創作活動の場とはなり得ない。